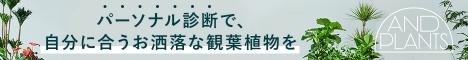サスティーを買ったけど、ずっと青いままで色が変わらない…
せっかく水やりのタイミングを知るために購入したのに、あてにならないんじゃないか
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は、サスティーが正常に機能しない場合でも、原因を特定して適切なメンテナンスを行えば、ほとんどの問題は解決できるんです。
この記事では、サスティーが青いままで色が変わらない原因と具体的な対処法、あてにならないと感じる場合の正しい使い方、そして長期間正常に機能させるためのメンテナンス方法について詳しく解説します。
- サスティーが青いままで色が変わらない主な原因と科学的な仕組み
- サスティーの正しい設置方法と鉢のサイズに合わせた選び方
- 色変化しない場合の具体的なメンテナンス方法と対処法
- サスティーの寿命とリフィル交換のタイミング・正しい手順
サスティーが青いままで色が変わらない場合の原因と対処法
-1.jpg)
サスティーの色が変わらず困っている方も多いでしょう。この問題は原因を知れば、ほとんどのケースで簡単に解決できます。以下の点について順に見ていきましょう。
- サスティーがずっと青いままになる主な原因
- サスティーの正常な色変化のタイミングと所要時間
- サスティーが青くならない・色が変わらない場合の対処法
- サスティーが水やり後にどのように反応するか
詳しく見ていきましょう。
サスティーがずっと青いままになる主な原因
サスティーが青いままで色が変わらない原因はいくつか考えられます。
- 給水口部の目詰まり
- 土質の問題
- 設置位置の不良
- リフィルの寿命
まず多いのが「目詰まり」の問題です。長期間使用しているとサスティーの給水口部に土中の不純物が蓄積し、水分の感知を妨げてしまいます。
また、土の質も重要な要素です。土の粒子が荒かったり、水はけが極端に良い土壌環境では、サスティーが水分を検知する前に水が流れ出てしまうケースがあります。
さらに、サスティーの設置位置も関係しています。サスティーの吸水部分が土の固まりや植物の根によって塞がれていると、水分の正確な検知ができなくなります。
使用期間も考慮すべき点で、約6~9ヶ月使用した後は内部の中芯(リフィル)が土中の微生物により分解されて機能しなくなっている可能性があります。
サスティーの正常な色変化のタイミングと所要時間
サスティーは正常に機能していれば、土壌の水分状態に応じて色が変化します。水やり後の青色から、土が乾燥すると白色に変わります。
この色の変化にかかる時間はサイズによって異なります。小さいSサイズは3分程度、中間のMサイズは15分前後、大きなLサイズだと約25分ほどかかるのが一般的です。
ただし、これは理想的な条件での時間であり、土壌の保水性によっては1時間以上かかる場合もあります。
色が変わる仕組みは、サスティーの中芯が毛細管現象を利用して水を吸い上げることで機能します。土壌の水分が「pF値」と呼ばれる有効水分域の範囲内にあるかどうかを判断し、視覚的に表示してくれるのです。
正確な水分測定のためには、適切な設置と十分な水やりが必要です。
サスティーが青くならない・色が変わらない場合の対処法
サスティーの色に変化が見られない時は、以下の対処方法を参考にしてください。
- 設置方法の確認・改善
- サスティーの根元にも水がかかるようにする
- 目詰まり解消
- 設置位置の改善
- リフィルの交換
最初に設置の仕方を確認することから始めましょう。適切な使用法としては、植物が植えられた鉢の中に本体のマーク部分まで差し込み、鉢全体に十分な量の水を与えることです。
特にサスティーの根元にも水がかかるようにすると効果的です。水やりの量は鉢の体積の4分の1から5分の1程度が適量です。
詰まりが生じている時は、熱湯に中性洗剤を少量加えたコップに、サスティーの小窓部分を下向きにして約1時間浸けておきます。その後、乾燥させて白くなるまで干せば再び使用できます。挿す位置も重要で、土を少しほぐしてから挿し直すと改善することがあります。
それでも色が変わらない場合は、リフィルの寿命が考えられます。約6~9ヶ月使用したら交換時期かもしれません。交換用のリフィルで新しくすることで問題が解決することが多いです。
サスティーが水やり後にどのように反応するか
適切に機能しているサスティーは、水やりを行うと青色へと変わります。変化のタイミングは鉢のサイズや土質によって異なりますが、一般的に数分から数十分で反応します。十分な水を与えたにもかかわらず色が変わらない場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。
水やり後の反応は、土壌が十分に湿っているかの指標となります。サスティーは「pF値2.0」という水分有効域で反応するよう設計されており、これは植物が根腐れや水枯れになる前のタイミングです。水やり後に青くなり、徐々に土が乾燥すると白に戻るというサイクルが正常な動作です。
この変化により、次の水やりのタイミングを視覚的に把握できるようになっています。あまりに早く白に戻る場合は水はけが良すぎる可能性があり、逆に長期間青いままの場合は排水が悪い、あるいはサスティー自体に問題がある可能性を考慮すべきです。
サスティーが水分計としてあてにならないと感じる場合の正しい使い方
-1-1.jpg)
サスティーの精度に疑問を感じている方もいるでしょう。適切な使い方を知れば、サスティーは信頼できる水分計になります。以下のポイントに注目して説明します。
- サスティーの正しい設置位置と挿し方
- サスティーが白くならない・色が変わらない理由
- サスティーの色変化の仕組みと原理
- 植物の種類や環境に合わせたサスティーの活用法
順番に解説していきます。
サスティーの正しい設置位置と挿し方
サスティーの効果を最大限に発揮させるためには、正しい設置方法が重要です。
まず、サスティーは植物の根が多い場所に挿すのが基本です。本体に表示されているマークの位置まで土に差し込みます。目安としては、計測部分が根の深さに埋まるようにするとよいでしょう。
設置する際は、土を少しほぐしてから挿すことで、サスティーの吸水口部がしっかりと土と接触できます。
また、根や硬くなった土が給水口をふさがないように注意しましょう。サスティーは鉢植えに挿してから水やりをすると、呼び水効果で変色しやすくなるという特性があります。
サイズ選びも重要です。小さい鉢(2〜3号)にはSサイズ、中程度の鉢(3.5〜6号)にはMサイズ、大きな鉢(6〜12号)にはLサイズが適しています。適切なサイズを選ぶことで、より正確な水分測定が可能になります。
サスティーが白くならない・色が変わらない理由
サスティーが白くならない場合、土壌がまだ十分に湿っている可能性が高いです。
特に経年劣化した硬い土は水はけが悪くなっているため、表面は乾いているように見えても中心部分はまだ湿っていることがよくあります。これは植物にとっては根腐れのリスクとなるため、植え替えを検討する必要があるかもしれません。
また、サスティーが反応しない原因として、土壌の質も影響します。水はけがよすぎる土質だと、サスティーが感知する前に水が流れ出てしまうため、色が変わらないことがあります。この場合は、水やりの際にサスティーの根元にも水をかけるようにすると改善します。
サスティーが古くなって機能が低下している可能性もあります。半年以上使っている場合は、経年劣化による目詰まりが起きていることも考えられます。メンテナンスやリフィルの交換を検討してみましょう。
サスティーの色変化の仕組みと原理
サスティーの色変化の仕組みは、毛細管現象と特殊な構造によるものです。本体には小窓があり、水分量で色が変わるリフィルが入っています。土壌に十分な水分があるときは青色、水分が減少すると白色に変化します。この変化は「pF値」という根が水を吸い上げる力を数値化した指標に基づいています。
サスティーは、根が乾燥を察知し、しおれる手前まで来たときにリフィルの色が変わるように設計されています。具体的には「pF値2.0」で変化するようになっており、これは根腐れや水枯れになる前の理想的なタイミングです。植物の空腹度とも言える指標を視覚化した、世界初の家庭用水分計なのです。
内部構造としては、リフィルが特殊な不織布でできており、中に青色のシートが含まれています。水分を吸い上げると内部の青色が透けて見え、乾燥すると白く見えるという仕組みです。電池や電気を使わないシンプルな構造ですが、科学的な原理に基づいた精度の高い製品なのです。
植物の種類や環境に合わせたサスティーの活用法
サスティーは基本的にどんな植物にも使用できますが、植物の特性を理解して活用することが重要です。
例えば、サボテンや多肉植物など乾燥を好む植物では、サスティーが白くなってからさらに数日待ってから水やりするといった調整が必要です。逆に湿り気を好む植物の場合は、サスティーが完全に白くなる前に水やりを行うことも検討できます。
季節による調整も大切です。成長期と休眠期では水やりの頻度が変わります。成長期はサスティーの指示通りに水やりをしてもよいですが、休眠期は植物の状態を見ながら調整が必要です。
特に冬場は、サスティーが白くなっても、すぐに水やりするのではなく、植物の状態を確認して判断しましょう。
また、サスティーはあくまで目安として考え、植物の様子と合わせて判断することが大切です。
葉のしおれ具合や土の表面の状態なども観察しながら、総合的に水やりのタイミングを決めると、より適切な植物管理が可能になります。
サスティーを「補助ツール」として位置づけ、自分の判断と併用することで、より効果的な活用ができるでしょう。
サスティーのメンテナンス方法とリフィル交換の重要性

サスティーの性能を長く保ちたいと思いませんか?定期的なメンテナンスとリフィル交換で長期間正確に使えます。以下のポイントを詳しく解説します。
- サスティーの寿命と交換時期の目安
- リフィル交換の正しい手順と注意点
- サスティーの性能を維持するための定期的なメンテナンス方法
- 土壌環境がサスティーの耐久性に与える影響
それぞれ詳しく見ていきましょう。
サスティーの寿命と交換時期の目安
サスティーのリフィル(中芯)は、自然由来の繊維で作られているため、時間の経過とともに土中の微生物によって分解されていきます。
一般的な寿命は約6~9ヶ月程度とされており、使用環境によって変わります。交換時期の目安は、水をあげても青くならなくなった時です。これは中芯が機能しなくなった証拠です。
サスティーの給水口部にある中芯が完全に分解してなくなっている場合は、機能が完全に停止しています。また、長期間使用していなくても、土中のバクテリア量によって耐用期間は変わるため、状態をこまめに確認することが大切です。
交換時期の見逃しは、植物の水やりタイミングを誤る原因になります。
サスティーを購入した時期を記録しておき、半年から9ヶ月経過したら交換を検討する習慣をつけると良いでしょう。定期的な交換により、常に正確な水分計測が可能になります。
リフィル交換の正しい手順と注意点
リフィルの交換は比較的簡単ですが、正しい手順で行うことが重要です。
土を傷めないよう優しく引き抜きましょう。
力を入れすぎないよう注意しながら回して外します。
崩れやすいので慎重に取り扱いましょう。
向きに注意して、奥までしっかり押し込みます。
マークの位置まで根の近くに差し込みます。
青色に変わるまで待ち、正常に動作するか確認します。
まず、鉢からサスティーを抜き、本体からキャップを外します。次に古いリフィルを取り出し、新しいリフィルを挿入します。この際、リフィルが本体にしっかりと収まっていることを確認しましょう。
交換時の注意点としては、中芯(リフィル)、青色シート、ストローの全てを必ず交換することです。まれにストローが本体の中に残ってしまうことがあるので、その場合はピンセットなどで取り除いてください。また、本体先端のネジキャップも外し、中に芯材が残っていないか確認することも大切です。
新しいリフィルは、使用するまでパッケージの内袋の中で保管してください。取り出すと芯材が黄変することがありますが、これは品質や効果には問題ありません。交換後は、サスティーを再び鉢に挿し、たっぷりと水をあげて正常に機能するか確認しましょう。
サスティーの性能を維持するための定期的なメンテナンス方法
サスティーの性能を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。特に目詰まりは頻繁に起こる問題です。使用を続けていると反応が鈍くなる場合、土中の不純物によって目詰まりしている可能性が高いです。
このような場合は、熱湯に中性洗剤を少量加えたコップに、サスティーの小窓部分を下向きにして約1時間浸けておきます。
これにより沈着している不純物が溶けて出てきます。その後、乾燥して白くなるまで干せば、目詰まりが解消され再び使用できるようになります。
また、サスティーを挿す土も時々軽くほぐしてあげると、給水口部の詰まりを防ぐことができます。
長期間同じ場所に挿していると、周囲の土が固まってしまうことがあるため、時々位置を変えてみるのも良い方法です。こうした簡単なメンテナンスを定期的に行うことで、サスティーの性能を長く保つことができます。
土壌環境がサスティーの耐久性に与える影響
土壌環境はサスティーの耐久性に大きく影響します。特に有機物が多く、微生物活動が活発な土壌では、リフィルの分解が早まる傾向があります。また、酸性度の高い土壌も材質の劣化を早める可能性があります。
水はけの悪い土壌では、サスティーの給水口部に常に水分が溜まりやすく、リフィルの寿命が短くなることがあります。逆に極端に乾燥する環境では、リフィル自体が乾燥して機能しなくなることも考えられます。
根の生長が旺盛な植物では、根がサスティーの周囲を取り囲み、水分の感知を妨げることがあります。このような場合は、定期的にサスティーの位置を少しずらすことで改善できます。
また、肥料の与えすぎは土壌中の塩類濃度を高め、サスティーのリフィル部分に塩類が付着して機能を低下させることがあります。
適切な土壌管理と植物管理を行うことで、サスティーの耐久性も向上します。定期的な植え替えや適切な施肥を心がけ、健全な土壌環境を維持することが、サスティーを長持ちさせるコツです。
サスティーが青いままで色が変わらない時に試すべき対処法のまとめ
最後に、この記事で紹介した内容をおさらいしましょう。
- サスティーが青いままで色が変わらない主な原因は目詰まりや土質の問題で、特に粒子が粗い土や水はけが極端に良い場合は水分検知前に水が流れ出てしまうことがある。
- サスティーの正確な使用法は本体のマークまで土に挿し込むことで、サイズ別では小さい鉢(2~3号)にはSサイズ、中程度(3.5~6号)にはMサイズ、大きな鉢(6~12号)にはLサイズが適している。
- 色変化しない場合の対処法として、熱湯に中性洗剤を少量加えたコップにサスティーの小窓部分を下向きにして約1時間浸し、その後乾燥させることで多くの場合改善する。
- サスティーのリフィル(中芯)は自然由来の繊維でできており、約6~9ヶ月で交換が必要で、交換時は中芯、青色シート、ストローの全てを新しいものに取り替えることが重要。
- 色の変化タイミングはサイズによって異なり、Sサイズで約3分、Mサイズで約15分、Lサイズで約25分が目安だが、土壌環境によって変動することも理解しておくべき。
これらのポイントを押さえれば、サスティーを正しく使いこなし、観葉植物の水やり管理をより正確に行うことができます。
サスティーはあくまで水やりのタイミングを知るための補助ツールです。植物の様子と合わせて判断することで、より効果的な植物管理が可能になります。
定期的なメンテナンスとリフィルの交換を忘れずに行いながら、あなたの大切な植物を健康に育てていきましょう。正しく使えば、サスティーは観葉植物初心者から上級者まで、水やり管理の強い味方になってくれるはずです。

-2-1.jpg)